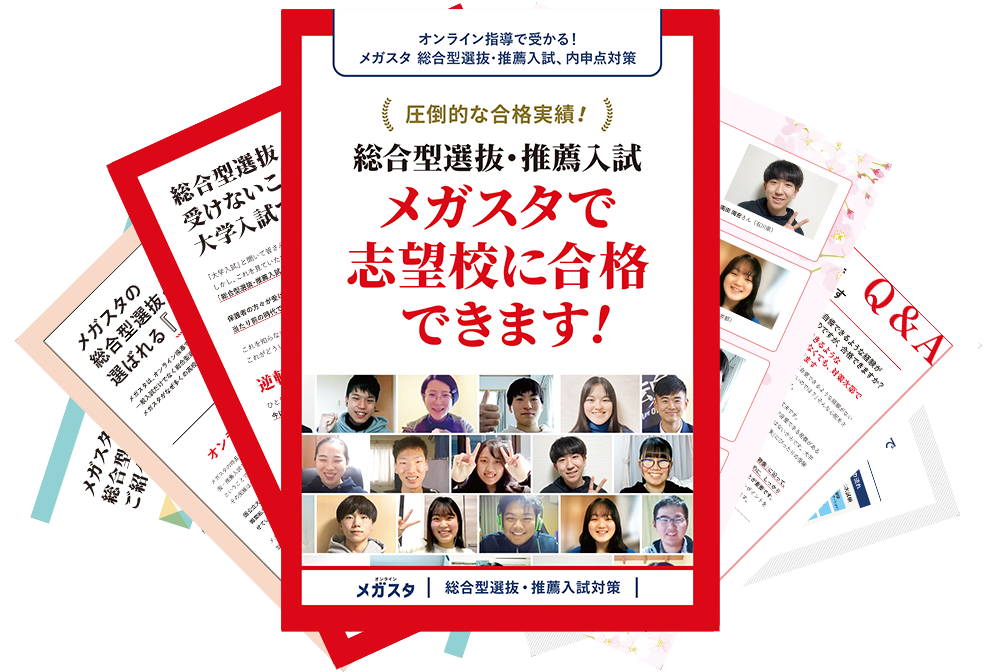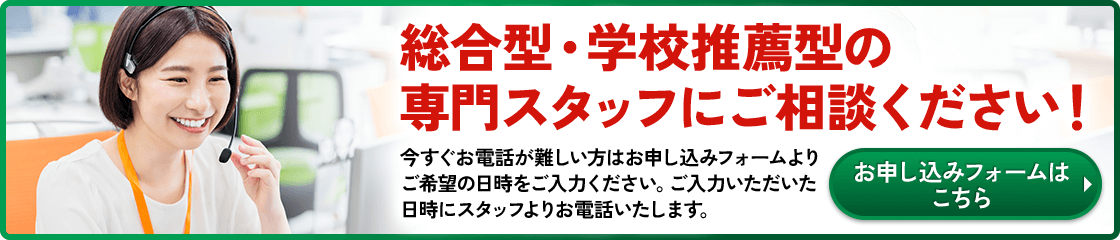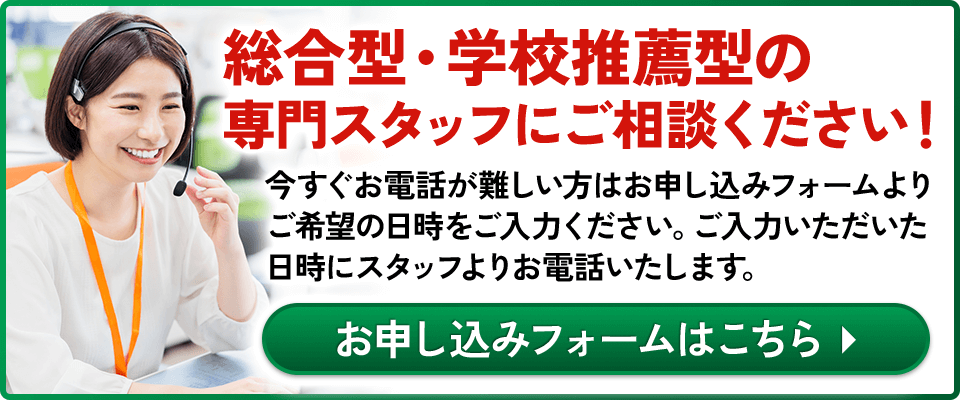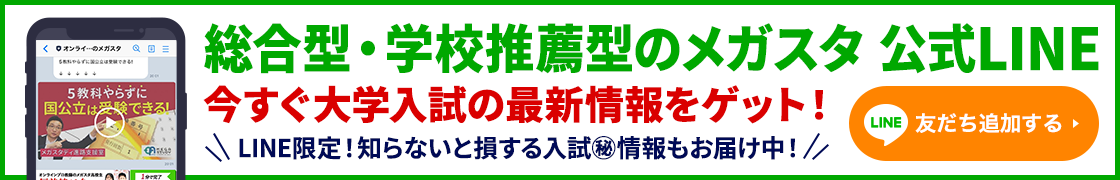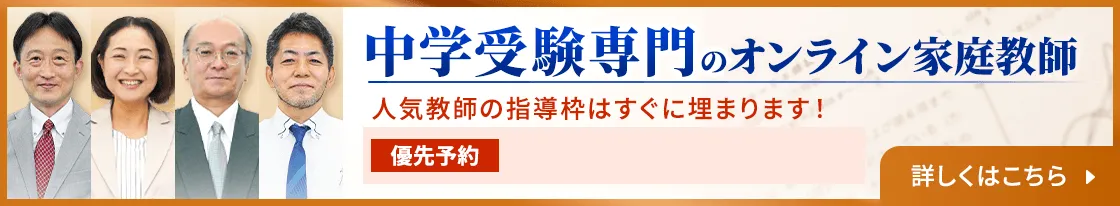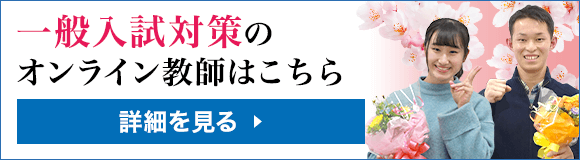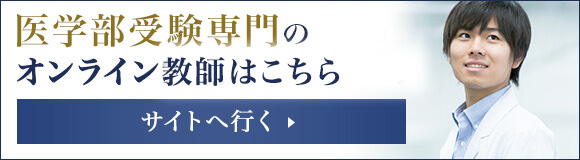総合型選抜対策で塾に行くべきか、行くべき人・不要な人の特徴、塾以外の対策法も解説
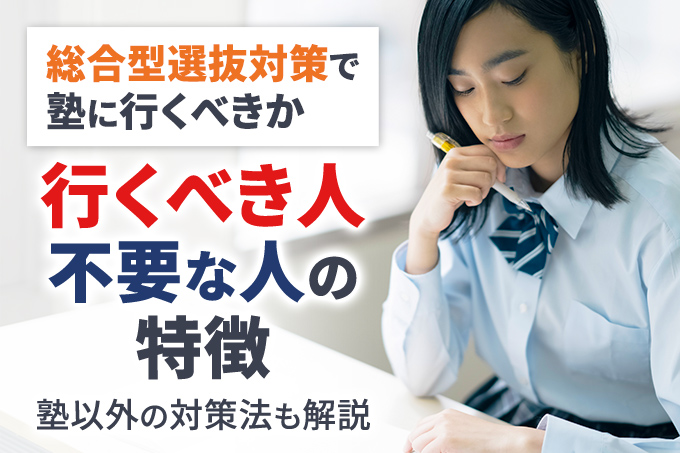
総合型選抜での大学受験を考えているけれど、
「対策のために塾へ行くべきか…」と悩んでいませんか?
周りが塾に通い始めると焦りを感じ、
独学だけで本当に合格できるのか不安になりますよね。
また、保護者の方にとっても、お子さんを塾に行かせるべきか、
決して安くない塾の費用に見合う効果があるのか、気になるところだと思います。
結論から言えば、総合型選抜の対策で塾が必須というわけでは決してありません。
一般・総合型などの受験方式を問わず、
塾に通わないで合格をされる方は毎年多くいらっしゃいます。
大切なのは、自身の性格や状況に合わせて最適な学習方法を選択することです。
この記事では、総合型選抜の対策で塾に行くべきかという重要な疑問に答えるため、
塾に行くべき人・不要な人の具体的な特徴を詳しく解説します。
さらに、塾を利用するメリット・デメリット、塾以外の対策方法、
そして後悔しない塾選びのポイントまで、この記事を最後まで読めば、
きっと自身の納得できる選択ができるようになるはずです。
目次
という方はメガスタの資料をご請求ください
サービス内容の詳細はこちら
向いているか診断!
自分の可能性を知ろう!LINEで無料診断
特典プレゼント!
総合型・学校推薦型選抜まるわかりBOOK
※特典は予告なく終了する場合がございます1 総合型選抜対策で塾は行くべきか
総合型選抜の対策や準備を進める上で、
多くの受験生が最初に直面するのが「塾に行くべきか」という問題です。
「周りが行っているから自分も行こう」というようなことにならないよう、
塾が必要かどうかを判断するための基本的な考え方について、まずは見ていきましょう。
【1】独学で対策できるなら塾は必要ない
総合型選抜の対策は、もし独学で合格レベルに到達できるのであれば、
塾に通う必要はまったくありません。
総合型選抜は、知識量を問う一般選抜とは異なり、あなた自身の経験や考え、
そして将来への熱意を問う入試です。
そのため、自分自身と深く向き合い、
大学側に伝えたいことを明確に言語化する作業が中心となります。
このプロセスを自分一人の力で、
あるいは学校の先生など身近な人の協力を得ながら進められるのであれば、
高額な費用をかけて塾に通う必然性はないと言えるでしょう。
ただし重要なのは、その「独学」が自己満足で終わっていないかという点です。
自分では完璧だと思った志望理由書も、プロの視点から見ればアピールが弱かったり、
論理が飛躍していたりすることは少なくありません。
独学で合格を目指すには、自分を客観視し、
質の高い対策を計画的に実行できる能力が不可欠です。
【2】総合型選抜で対策塾へ行くべき人・不要な人の特徴
では、ご自身が塾を利用すべきか否かを判断するために、
具体的な特徴を対比して見ていきましょう。
まず、塾に行かなくても合格を目指せる可能性が高い人には、
以下のような特徴があります。
- 自己分析が得意で、自分の強みや経験を言語化できる
- 志望大学のアドミッション・ポリシーを深く理解し、それに沿ったアピールができる
- 論理的で分かりやすい文章構成力がある
- 信頼できる第三者(文章指導に長けた高校の先生など)に、質の高いフィードバックをもらえる環境がある
要するに、これらは「自走できる“能力”と“環境”が整っている人」と言い換えられます。
これらの条件が揃っていれば、独学でも十分に合格を狙えるでしょう。
一方で、次のような悩みや不安を一つでも抱えている場合は、
対策塾の利用を積極的に検討することをおすすめします。
- 自分の書いた志望理由書や小論文が良いのか悪いのか、客観的な判断ができない
- 面接で何をどう話せば評価されるのか分からず、実践的な練習相手がいない
- 学校の先生や親のアドバイスだけでは、専門的な対策に不安が残る
総合型選抜は情報戦の側面もあり、専門性が高い入試です。
自分一人での対策に限界を感じたり、プロの視点から厳しい指摘や
具体的な改善指導を受け、合格の可能性を少しでも高めたいと考えていたりするならば、
塾は非常に心強い存在となるはずです。
2 知っておきたい!総合型選抜で必要な対策

総合型選抜の対策を効果的に進めるためには、
まず「何を備えるべきか」を正確に知ることが不可欠です。
大学や学部によって試験内容は多岐にわたりますが、多くの大学で共通して課され、
合否に直結する重要な要素が存在します。
特に、「活動報告書・志望理由書」「小論文」「面接」の3つは、
総合型選抜の核となる対策項目です。
これらはそれぞれ別物に見えますが、
実は一貫したあなたの人物像や学習意欲を伝えるという点で、深く結びついています。
ここでは、それぞれの対策で具体的に何が求められるのかを簡単に解説します。
総合型選抜についてより詳しく知りたい方は
「総合型選抜とは?受験のメリットや注意点、対策のポイントも解説!」の記事も
あわせてチェックしてみてください。
【1】活動報告書・志望理由書の対策
「活動報告書」や「志望理由書」といった提出書類は、
総合型選抜の合否を左右する土台となる、最も重要な要素です。
これらの書類は面接での質問のベースとなり、あなたの第一印象を決定づけます。
ここでの評価が低いと、その後の選考で挽回するのは非常に難しくなるでしょう。
これらの書類で大学側が知りたいのは、単なる活動実績の羅列ではありません。
「部活動で部長を務めた」「ボランティアに参加した」という事実だけでなく、
その経験を通じて何を学び、どのような課題意識を持ち、
それが志望大学・学部での学びにどう繋がるのかという一貫したストーリーです。
そのため、対策の第一歩は徹底した「自己分析」と「大学研究」に尽きます。
自分の過去の経験を深く掘り下げて自分の価値観や強みを理解し、
同時に、大学が公開している「アドミッション・ポリシー」やカリキュラムを
隅々まで読み込むことで、自分と大学との接点を見つけ出し、
説得力のある物語を構築していく作業が求められます。
関連コラム:総合型・学校推薦型選抜合格に活かせる活動とは?活動報告書の例も紹介!
参照:アドミッション・ポリシーとは?言葉の意味と3つのポリシーの解説に大学の具体例も紹介|逆引き大学辞典
【2】小論文対策
小論文は、あなたの論理的思考力、文章表現力、
そして物事に対する洞察力を測るための試験です。
感想文や作文とは異なり、与えられた課題やテーマに対して、
明確な根拠に基づき自分の意見を筋道立てて説明する能力が求められます。
出題されるテーマは、学部に関連する専門的な内容から、
社会問題や時事問題まで多岐にわたります。
対策の基本は、まず志望大学の過去問を分析し、出題の傾向を把握することです。
その上で、日頃から新聞やニュースに目を通し、社会で起きている出来事に対して
「なぜそうなっているのか」「自分ならどう考えるか」と
自分なりの意見を持つ習慣をつけることが非常に重要になります。
また、書き上げた小論文は必ず信頼できる第三者に読んでもらい、
添削を受けるようにしましょう。
自分では気づきにくい論理の飛躍や分かりにくい表現を客観的に指摘してもらうことで、
文章の質は格段に向上します。
【3】面接対策
面接は、書類だけでは伝わらないあなたの個性や熱意、
コミュニケーション能力を総合的に評価される場です。
提出した書類に書かれている人物が本当に魅力的であるか、
大学の求める学生像と合致しているかを見極める、
いわば最終確認の場と言えるでしょう。
面接官は、あなたが質問にただスラスラと答えられるかを見ているわけではありません。
質問の意図を正確に理解し、自分の言葉で論理的に回答できるか、
そして何よりも「この大学で学びたい」という強い情熱を持っているかを重視しています。
自信のある態度や明るい表情、丁寧な言葉遣いといった、
人としての印象も大切な評価ポイントです。
対策として最も重要なのは、実践形式の模擬面接を可能な限り多く経験することです。
学校の先生や家族、塾の教師などに協力してもらい、
本番さながらの緊張感の中で受け答えの練習を繰り返しましょう。
何度も練習することで、不意の質問にも落ち着いて対応できる力が身につき、
自信を持って本番に臨めるようになります。
3 総合型選抜を個人で対策するなら?
塾を利用せずに総合型選抜の合格を目指す場合、
ここまでご紹介してきたような各対策について、すべてを自分自身で管理し、
能動的に行動していく必要があります。
ここでは、個人で対策を進める上で特に重要となる3つのポイントを紹介します。
【1】試験で活かせる活動実績を作る
総合型選抜では、あなたの個性や行動力、探究心が評価されます。
そして、それらを客観的に証明するものが、高校生活における「活動実績」です。
部活動、生徒会活動、ボランティア、資格取得(英検®など)、探究学習の成果など、
アピールできる活動は多岐にわたります。
ただし、単に「○○をしました」という事実の羅列だけでは、
評価者の心には響きません。
先ほどのパートでもご紹介したように、最も大切なのは
「なぜその活動に取り組み、どんな課題意識を持って、
どのように行動したのか」というプロセスです。
「チームをまとめるためにどんな工夫をしたか」
「探究学習で浮かび上がった新たな疑問は何か」
といった経験の深掘りこそが、あなただけのオリジナルな物語となります。
これらの経験は、志望理由書や面接で説得力を持って自分をアピールするための
強力な武器になります。
高校1・2年生のうちから様々なことに主体的にチャレンジし、
自分だけの物語の「種」を育んでおくことが非常に重要です。
【2】大学の情報を徹底的に調べる
活動実績と並行して、独学で対策する上での生命線となるのが、
志望大学に関する徹底的な情報収集です。
総合型選抜は、大学と受験生との相性(マッチング)を重視する入試です。
そのため、
「数ある大学の中で、なぜこの大学のこの学部でなければならないのか」
という問いに、具体的かつ説得力のある答えを用意する必要があります。
その答えを見つけるために、まずは大学のウェブサイトを隅々まで読み込みましょう。
特に、大学が「どのような学生に来てほしいか」を明記している
「アドミッション・ポリシー(入学者受入方針)」は、
対策のコンパスとなる最も重要な文書です。
志望する大学の「アドミッション・ポリシー」については、必ず熟読してください。
さらに、学部で学べる授業内容やカリキュラム、
教授の専門分野や研究テーマまで深く調べることで、
「この教授のゼミで○○を学びたい」といった、
より具体的で熱意の伝わる志望理由を語れるようになります。
オープンキャンパスやオンライン説明会への参加も、
大学の雰囲気を肌で感じ、有益な情報を得る絶好の機会です。
こうした地道な情報収集が、ライバルと差がつく
「深い志望理由書」を作成するための鍵となります。
【3】学校の先生に面接対策をお願いする
書類作成や大学研究とは異なり、
面接対策だけは自分一人で完結させることができません。
独学で進める場合、実践的な面接練習の機会をいかに確保するかが課題となりますが、
そこで最も身近で頼りになるのが学校の先生です。
進路指導の先生はもちろん、クラスの担任や教科担当、
部活動の顧問の先生などにお願いして、ぜひ模擬面接を行ってもらいましょう。
多くの生徒を指導してきた先生方は教育のプロです。
あなたのことをよく理解した上で、自分では気づかない話し方の癖や表情、
回答の改善点などを客観的に指摘してくれるはずです。
たとえ先生が総合型選抜の専門家ではなかったとしても、
本番同様の緊張感の中で、
大人を相手に自分の考えを話す練習をすること自体に大きな価値があります。
大切なのは、ただ丸投げするのではなく、
自分で用意した想定問答を持参するなど、主体的に協力を求める姿勢です。
この練習の積み重ねが、きっと本番での自信に繋がるでしょう。
4 総合型選抜の対策で塾を利用するメリット

ここまで独学での対策方法について解説してきましたが、
実際には自分の実績の何をどのようにアピールすればいいのか分からなかったり、
大学の情報を調べたものの
「志望理由書」にどう落とし込めばいいのか分からなかったり、
身近な先生が忙しく模擬面接の時間を取れないということも、
現実問題として考えられるでしょう。
そうした独学の限界や不安を解消し、
合格の可能性を大きく高めてくれるのが専門の対策塾です。
ここでは、総合型選抜の対策で塾を利用する主なメリットを3つの観点から
具体的に解説します。
これらのメリットが自分にとって必要かを考えることが、
塾に通うべきかどうかの判断基準になるでしょう。
【1】プロによる指導とフィードバック
塾を利用する最大のメリットは、総合型選抜を熟知したプロによる専門的な指導と、
的確なフィードバックを受けられる点にあります。
塾の講師は、毎年多くの受験生を合格に導いてきた、
いわば入試のプロフェッショナルです。
彼らは、大学がどのような基準で受験生を評価し、
何をアピールすれば合格に近づくのかという「採点者の視点」を持っています。
自分では完璧だと思った志望理由書も、プロから見れば
「これでは熱意が伝わらない」「アピールすべき強みがずれている」など、
合否に直結する改善点が見つかることが少なくありません。
また、面接指導においても、単なる練習相手ではなく、
「その回答では質問の意図を汲み取れていない」といった、
合格から逆算した厳しいながらも的確な指摘を受けることができます。
この質の高いフィードバックは、友人や家族、
そして多忙な学校の先生からだけでは得ることが難しい、
専門塾ならではの価値と言えるでしょう。
【2】豊富な大学情報と受験合格ノウハウ
総合型選抜は「情報戦」の側面が非常に強い入試です。
専門の対策塾を利用すれば、個人で収集するには限界がある、
豊富で質の高い情報を得ることができます。
例えば、ウェブサイトを見るだけでは分からない
「学部ごとの面接の雰囲気の違い」や「過去に評価された小論文のテーマ」といった、
より実践的な情報を得ることができるでしょう。
また、塾には「どのような活動実績を持つ生徒が合格したか」
「どのような志望理由書が評価されにくいか」といった、
過去の成功・失敗事例がデータとして蓄積されています。
こうした膨大なデータに基づいた合格ノウハウは、
独学で手に入れることは極めて困難です。
入試制度は年々変化しますが、専門塾は常に最新の動向を分析しているため、
その年に合わせた効果的な戦略を立てるためのサポートをしてくれます。
こういった情報アドバンテージを得られることは、
塾を利用する大きなメリットの一つです。
【3】計画的な学習スケジュール
総合型選抜は出願時期が早く、高校3年生の夏から秋が本番となります。
学校の定期試験や学校行事、そして一般選抜に向けた勉強と並行して
対策を進める必要があり、個人でのスケジュール管理は想像以上に困難です。
専門の塾では、あなたの志望校の入試日から逆算して、
「いつまでに自己分析を終え、いつから志望理由書の作成に取り掛かり、
何回面接練習を行うか」といった、具体的で無理のない学習計画を立ててくれます。
やるべきことが明確になるだけでなく、
塾のスケジュールが自分のペースメーカーとなり、
対策の遅れや中だるみを防ぐ効果も期待できます。
「自分一人だと、つい後回しにしてしまいそう…」という不安がある人にとって、
学習を半強制的にでも進められる環境は大きなメリットです。
計画的に準備を進められる安心感は、受験期の精神的な安定にも繋がるはずです。
5 総合型選抜の対策で塾を利用するデメリット
ここまで総合型選抜で塾へ行くべきか悩んでいる高校生や
その保護者の方に向けて塾利用をするメリットを解説してきましたが、
自身の状況に最適な判断をするためには、
塾を利用するうえでのデメリットもしっかりと理解しておくことが重要です。
ここでは塾を利用する場合に考えられる、
いくつかのデメリットを確認していきましょう。
【1】経済的な負担が発生する
塾の利用を考える上で、最も大きな障壁となるのが経済的な負担です。
総合型選抜の対策塾は、専門性の高い指導や個別対応が中心となるため、
一般的な学習塾に比べて費用が高額になる傾向があります。
受講するコースにもよりますが、年間で数十万円から、
場合によっては100万円を超える費用がかかることもあり、
ご家庭にとっては決して軽い負担ではありません。
ただ、この費用については長期的な視点で考えてみることも大切です。
もし対策がうまくいかず不合格となり、浪人することになれば、
予備校の費用などでさらに大きなコストが発生する可能性もあります。
もちろん塾に通えば100%合格できるわけではありませんが、
第一志望校への現役合格の可能性を高めるための
「未来への投資」と捉えることもできます。
この費用対効果をどう考えるか、
ご家庭でしっかりと話し合って判断することが重要です。
【2】通塾の時間や手間がかかる
見過ごされがちですが、通塾に要する時間的なコストも無視できないポイントです。
塾が自宅や学校から離れている場合、
往復の移動時間が貴重な学習時間を圧迫してしまう可能性があります。
特に、部活動や学校行事で忙しい高校生活の中、
決められた時間に塾へ通うこと自体が大きな負担になりかねません。
移動による体力的な消耗が、かえって勉強の効率を下げてしまうことも考えられます。
また、お住まいの地域によっては、
総合型選抜を専門に扱う塾が近くに存在しないという問題もあるでしょう。
限られた受験期の時間を最大限に活用するためにも、
通塾にかかる時間や労力が得られるメリットと見合っているか、
自身の生活スタイルと照らし合わせて検討することが大切です。
【3】教師や指導内容が自分に合わないリスク
「担当する教師の指導スタイルや塾の方針が、必ずしも自分に合うとは限らない」という
人間関係・指導方針のズレに関するリスクも考慮しておく必要があるでしょう。
この点は、自分自身の内面をさらけ出し、
教師と二人三脚で進めていく総合型選抜の対策においては、
特に重要なポイントになります。
例えば、手厚く褒めて伸ばしてほしいタイプの生徒さんが、
厳しい指摘で成長を促すタイプの教師に担当されてしまうと、
モチベーションの低下に繋がるかもしれません。
また、単純に教師との人間的な相性が合わない可能性もあります。
このようなミスマッチが起きた場合、指導者との信頼関係を築けず、
対策の質そのものに致命的な影響を与えかねません。
入塾前に相性を完全に見極めるのは難しいですが、
多くの塾では担当教師を簡単に変更できないケースも多いのが実情です。
高額な費用を払うからこそ、このようなリスクがあることも理解しておくべきでしょう。
6 総合型選抜を塾以外で対策する方法
ここまでご説明してきたようなデメリットを見て、
「経済的な事情で難しい」「部活動が忙しくて通塾の時間は取れない」
「そもそも近所に専門塾がない」
といったことを思われた方もいるのではないでしょうか?
ですが、そういった方でも決して諦める必要はありません。
近年では、従来の通塾型の塾以外にも、
総合型選抜の対策を効果的に進めるための選択肢が数多く登場しています。
その代表格が、インターネットを活用したオンラインでの指導サービスです。
費用面については集団か個別指導かといった指導体制によっても変わりますが、
通学塾と比べて費用が安くなるケースも多いです。
参照:オンライン塾の授業料は、対面式の塾と比較してどれくらい安い?|コエテコ by GMO
また、オンライン指導であれば通塾にかかる移動時間がゼロになるため、
時間を最大限に有効活用できるうえ、住んでいる場所に関係なく、
全国の優れた講師による専門的な指導を自宅で受けることができます。
「通塾」という限られた選択肢の中では難しいですが、オンラインであれば、
自身にあった教師に出会える可能性も大きく高まるでしょう。
7 総合型選抜の対策塾やオンライン指導を選ぶ際のポイント

他のサービスと同じように、塾やオンライン指導も
「どこでも中身は同じ」というわけでは決してありません。
特に総合型選抜は、指導者の専門性や経験が結果を大きく左右するため、
サービス選びは慎重に行う必要があります。
後から「こんなはずではなかった…」と後悔しないために、
自身に最適な対策塾やオンライン指導を選ぶ際のポイントをご紹介します。
【1】総合型選抜の合格実績があるか
塾やオンライン指導を選ぶ上で、まず確認すべき最も客観的な指標が
「総合型選抜における合格実績」です。
豊富な合格実績は、そのサービスが持つ指導ノウハウや情報量の質を証明する、
何よりの証拠となります。
ただし、単に「合格者数〇〇名」という全体の数字だけを見るのではなく、
その中身を詳しく確認することが重要です。
自身が目指す大学や学部系統の合格実績が豊富かどうかも必ずチェックしましょう。
また、塾での指導とオンラインの指導では、指導の仕方やポイントも変わってきます。
オンラインのサービスを選ぶ際には、「オンライン指導の実績がどうか」という点も
確認しておくことが大切です。
関連ページ:オンライン家庭教師メガスタのオンライン指導とは
【2】志望大学・学部に特化した対策ができるか
総合型選抜は、大学・学部ごとに評価基準、選考内容、出題傾向が大きく異なります。
ある大学では小論文が重視される一方で、
別の大学ではグループディスカッションが課されるなど、その対策は千差万別です。
そのため、ただ漠然と「総合型選抜対策」を掲げているだけでなく、
あなたの志望大学・学部に特化した、専門的な対策カリキュラムが
用意されているかを確認することが極めて重要です。
サービスを選ぶ際には、「志望校別のコースが設置されているか」
「志望する大学・学部の指導実績があるか」といった点を必ずチェックしましょう。
志望校の傾向を熟知した上で対策を進めることで、やるべきことが明確になり、
無駄なく効率的に合格を目指すことができます。
8 総合型選抜をオンラインで対策するならメガスタへ!

ここまで、総合型選抜の対策や、塾・オンライン指導を選ぶ上でのポイントを
解説してきました。
「豊富な合格実績」「自分に合う教師」「志望校別の専門対策」といった条件を
すべて満たすサービスを見つけるのは、簡単ではないと感じるかもしれません。
もしあなたがオンラインでの対策を少しでも考えていて、
どこにすべきか迷っているなら、オンライン塾のメガスタにまずご相談ください。
メガスタは、総合型・学校推薦型選抜でオンライン指導における
日本最大級の合格実績を誇り、その専門的な指導を
多くの生徒さんやその保護者、メディアの方にもご評価いただいています。
まずは無料の資料請求やオンライン説明会に参加して、
メガスタがどのような指導を行っているのか、
ご自身の目で確かめてみてはいかがでしょうか。
専門のスタッフが、あなたの悩みや疑問に丁寧に答えてくれます。
9 総合型選抜で合格した先輩の声はこちら!
早稲田に合格! 早稲田大学(スポーツ科学部)合格
麻生 友美さん(岩手県)

メガスタの指導を受けて、志望理由書の書き方がわかったのはもちろんですが、それ以上に考え方の幅が広がったことが一番大きな変化です。普段のメガスタの授業での担当の先生との会話を通して、スポーツだけでなく他分野の知識を取り入れることができ、小論文や面接の際にも活かすことができました。

総合型で合格! 滋賀大学(データサイエンス学部)合格
福田 良さん(兵庫県)

自分の学力が足りていない状態で受かることができたのでとてもうれしいです。志望理由書や面接において何が大切か、大学側が何を求めているのかなどの総合型選抜にといて大事な点を深く学べたことが一番よかった点だったと思います。文章の書き方やストーリー性を持たせて書くことを教えていただきました。

東科大に合格! 東京理科大学(工学部)合格
本多 恭華さん(東京都)

メガスタの指導を受けてから、自分の思いが読み手にきちんと伝わる文章を書くことができるようになったと感じています。小論文に関しても、書き方が全く分からない状態からのスタートでしたが、今では楽しく書き進められるほどに成長することができました。志望理由書や小論文の指導以外にも、勉強計画のサポートや大学に提出するポートフォリオの確認などもしてくださりました。

メガスタでは、2025年度入試においても、
北は北海道から南は沖縄まで、全国の受験生をオンラインでサポートし、
国公立から早慶上智、MARCH、関関同立といった難関私立大学まで、
数多くの合格者を輩出しています。
偏差値40台からの逆転合格、部活動と両立しながらの難関大合格、
地方から挑んだ憧れの大学への合格など、一人ひとりの状況に合わせた指導で、
多くの先輩が夢を叶えました。
数多くの合格体験記を専用ページでご紹介しています。ぜひご覧ください。
この記事の著者
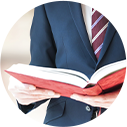
メガスタ編集部(メガスタヘンシュウブ)
総合型選抜・学校推薦型選抜に関する最新情報をわかりやすく発信する、教育情報メディアの編集部です。受験対策や準備のポイント、大学選びに役立つ知識を、丁寧に解説します。