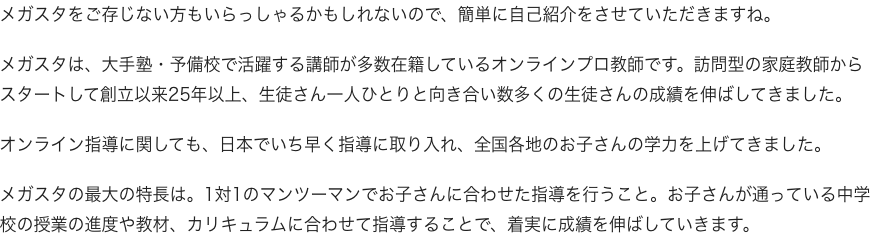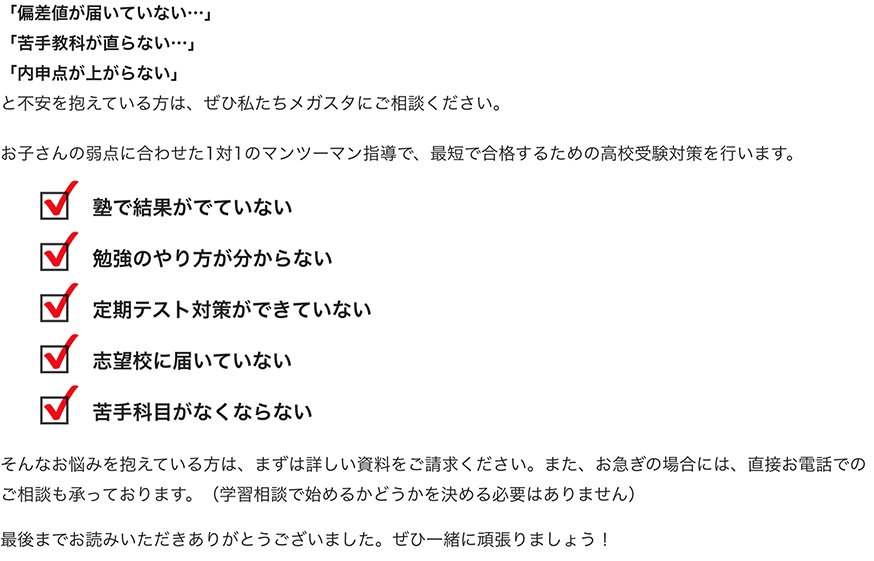長野県の公立高校受験対策!
メガスタの高校受験対策とは?
このページでは、長野県の公立高校に合格を目指す方のために、長野県の公立高校入試の仕組みや志望校に合格するためのポイントについて紹介しています。ぜひ公立高校受験対策にお役立てください。
2025年度の長野県の高校入試は以下の通り実施されました。
2026年度の入試スケジュールもほぼ同様の日程で実施される見込みです。
前期選抜
| 出願受付日 | 2月3日~2月5日 |
|---|---|
| 検査日 | 2月10日 |
| 合格発表日 | 2月19日 |
後期選抜
| 出願受付日 | 2月26日〜2月28日 |
|---|---|
| 志願変更日 | 3月3日~3月5日 |
| 検査日 | 3月11日 |
| 追検査日 | 3月17日 |
| 合格発表日 | 3月21日 |
※日程や入試要項は変更となる場合があります。最新の情報は教育委員会が発表する入試要項を確認してください。
基本的なことですが、出願や試験日などの日程はしっかりとおさえておきましょう。
ここからは主に、学力試験と内申点の対策についてご紹介していきます。 高校入試の仕組みを理解しないせいで、入試直前に後悔してしまったり、損をしてしまう生徒さんが毎年大勢います。少し長いですが、ぜひ最後までお読みください。
1中学3年生の内申点 45点満点
2学科試験の点数 5教科×100点 500点満点
3面接
| 中学3年 | 9教科×5段階評価 = 45点満点 |
|---|
| 試験時間 | 50分 |
| 配点 | 100点 |
| 大問数 | 5問 |
大問1は論説文からの出題。漢字の読みや空欄補充など基本的な問題から自分の考えを述べる90字程度の作文問題が出題されます。 大問2以降は話し合い問題、大問3に漢字問題、大問4に古文など、比較的配点が少なめの問題が続きます。 最後に大問5で小説問題が出題され、論説文に続きここでも50字程度の記述問題が出題されます。 問題を解く際にはどの問題を優先的に解答するべきかをあらかじめ決めて臨むとよいでしょう。
| 試験時間 | 50分 |
| 配点 | 100点 |
| 大問数 | 4問 |
大問1は小問集合問題が12問出題。全体を通しても配点が36点分と最も高いため、確実に得点できるようにしましょう。 大問2では方程式などの文章問題の出題や回転体に関する問題。作図問題も例年出題傾向にあります。 大問3以降はグラフの読み取りや、条件変更による解法を求められる問題や図形を用いた証明問題が出題されています。 特に図形の証明問題は例年出ている重要な問題のため、しっかり対策を行いましょう。
| 試験時間 | 50分 |
| 配点 | 100点 |
| 大問数 | 4問 |
大問1はリスニング問題。適切な絵を選択する問題や、会話を聞いて、正しい文などを選択する問題がほとんどです。 大問2は例年会話文のやりとりをよみ、内容一致や適語を選択する問題となっています。また、作文も出題されています。 大問3・4は長文読解問題で空所補充や内容一致問題、英作文などが出題されます。 長文は比較的長めの文章になっているため、素早く正確に内容を把握するようにしましょう。
| 試験時間 | 50分 |
| 配点 | 100点 |
| 大問数 | 4問 |
大問1は生物からの出題で記号選択問題のほかに語句記述問題や短文の記述問題が出題。 大問2では化学からの出題となっており、グラフの作成などが見られます。 大問3は地学からの出題。記述問題のほか、計算問題なども出題されます。大問4は物理からの出題で作図問題など出題されています。 大問それぞれ25点ずつの配点となっており、理科4分野からまんべんなく出題されるため、苦手科目がないように対策をしましょう。
| 試験時間 | 50分 |
| 配点 | 100点 |
| 大問数 | 3問 |
大問3問構成となっており、地理、歴史、公民とそれぞれの分野から1問ずつ出題されています。 他の県に比べ、記述問題の割合が高く、効率よく解答しないと時間が足りなくなる可能性があります。 また、資料の読解やグラフ・表を用いた問題が多いため、資料を正確に読み解くように対策をする必要があります。
1中学3年の内申点
2入試本番の学科試験の点数
詳しくはメガスタの定期テスト対策ページをご覧ください

長野県長野工業高等学校 長野県長野高等学校 長野県長野商業高等学校 長野県長野西高等学校 長野県長野東高等学校 長野県長野南高等学校 長野県長野吉田高等学校 長野県篠ノ井高等学校 長野県更級農業高等学校 長野県松代高等学校 長野市立長野高等学校 長野工業高等専門学校 長野清泉女学院高等学校 長野俊英高等学校 長野女子高等学校 長野日本大学高等学校 文化学園長野高等学校
長野県梓川高等学校 長野県松本県ヶ丘高等学校 長野県松本蟻ヶ崎高等学校 長野県松本工業高等学校 長野県松本深志高等学校 長野県松本美須々ヶ丘高等学校 エクセラン高等学校 信濃むつみ高等学校 松商学園高等学校 松本第一高等学校 松本秀峰中等教育学校 松本国際高等学校
長野県上田高等学校 長野県上田染谷丘高等学校 長野県上田千曲高等学校 長野県上田東高等学校 長野県丸子修学館高等学校 上田西高等学校 さくら国際高等学校 コードアカデミー高等学校
長野県岡谷工業高等学校 長野県岡谷東高等学校 長野県岡谷南高等学校
長野県飯田高等学校 長野県飯田OIDE長姫高等学校 長野県飯田風越高等学校 長野県下伊那農業高等学校 飯田女子高等学校
長野県諏訪実業高等学校 長野県諏訪清陵高等学校 長野県諏訪二葉高等学校
長野県須坂高等学校 長野県須坂創成高等学校 長野県須坂東高等学校
長野県小諸高等学校 長野県小諸商業高等学校
長野県高遠高等学校 長野県伊那北高等学校 長野県伊那弥生ヶ丘高等学校 伊那西高等学校
長野県赤穂高等学校 長野県駒ヶ根工業高等学校
長野県中野西高等学校 長野県中野立志館高等学校
長野県大町岳陽高等学校
長野県飯山高等学校
長野県茅野高等学校 東海大学付属諏訪高等学校
長野県田川高等学校 長野県塩尻志学館高等学校 東京都市大学塩尻高等学校
長野県望月高等学校 長野県岩村田高等学校 長野県佐久平総合技術高等学校 長野県野沢北高等学校 長野県野沢南高等学校 佐久長聖高等学校 地球環境高等学校
長野県屋代高等学校 長野県屋代南高等学校
長野県東御清翔高等学校
長野県明科高等学校 長野県豊科高等学校 長野県南安曇農業高等学校 長野県穂高商業高等学校
長野県小海高等学校
長野県軽井沢高等学校 長野県蓼科高等学校 インターナショナルスクール・オブ・アジア軽井沢
長野県下諏訪向陽高等学校 長野県富士見高等学校
長野県辰野高等学校 長野県上伊那農業高等学校 長野県箕輪進修高等学校
長野県阿智高等学校 長野県阿南高等学校 長野県松川高等学校 天龍興譲高等学校
長野県蘇南高等学校 長野県木曽青峰高等学校 緑誠蘭高等学校
日本ウェルネス長野高等学校
長野県池田工業高等学校 長野県白馬高等学校
長野県坂城高等学校
長野県下高井農林高等学校
長野県北部高等学校
長野県の私立高校の入試は試験日程や選抜方法などを独自に決めています。大きく分類すると1月初旬から開始される「推薦入学者選抜」と2月初旬から実施される「一般入学者選抜」に分けられます。ごく稀に12月下旬や1月初旬に一般入試を行う学校もあります。
私立高校の推薦入学者選抜は学校長推薦と自己推薦の2種類があります。
学校長推薦で受験するには各学校が定める内申点や部活動などの成績の基準を満たす必要があり、合格したら必ずその高校に入学しないといけない決まりがあります。選抜は面接と調査書、推薦書の内容を見て総合的に判断されます。作文や美術系の学科によっては実技があるため各学校の入試要項を事前に確認しておきましょう。
自己推薦の受験方法は専願と併願の両方あります。ただし自己推薦を行っていない学校や専願のみ受け付けている学校など様々なパターンがあるので、志望校の入試要項の確認が必須です。また選抜方法は面接と作文、推薦書などで学力テストを行わないケースが多くなっています。
次に私立高校の一般入学者選抜についてご紹介します。長野県の私立高校の一般入試は基本的に併願が可能ですが、専願のみの場合もあります。
学力テストメインで選抜が行われており、5教科もしくは3教科で試験が実施されます。試験内容は学校によって異なり、面接試験が課される場合もあるためテスト対策と並行して面接の準備も必要です。
また3月下旬ごろ定員に達しなかった学校では第二次募集が行われるため、公立高校に不合格になってしまった場合も私立高校を受けられることになります。
公立高校を第一志望とする生徒さんが私立高校を併願することのメリットとして、試験慣れできることや合格している高校があることで安心感を得られることが挙げられます。 試験に慣れておくことはとても重要で、初めての受験は緊張して実力を発揮できなかったという声をよく耳にします。1度本番の試験を受けておけば、試験会場の雰囲気に慣れて志望校の試験には落ち着いて臨むことができますよね。また万が一第一志望の学校に落ちたとしても入学する高校があることで、余裕を持って試験や受験勉強に取り組むことができます。
公立高校が第一志望の生徒さんも私立高校の併願受験を視野に入れて入試時期のスケジュール計画を立てていきましょう。
長野県の公立高校の推薦入試は前期選抜と呼ばれる「自己推薦型選抜」があります。 「自己推薦」形式で中学校長の推薦は不要です。各高校が定める募集要項の観点に応じてだれでも志願ができます。2021年には全日制課程において前期選抜を実施した公立高校は62校で、一部の学校では前期選抜は行われていません。募集は専門学科・総合学科と一部の普通科で行われ、学校・学科によっては募集定員を90%以内に設定しています。このように前期選抜の定員の比率が高い学校は後期選抜での募集枠がかなり少なくなるため、事前に確認しておくことが必要です。
試験内容は前期選抜を実施した全ての学校で志願理由書(または自己PR文)と面接による選考が行われるほか、学校によっては作文(小論文)や実技試験が実施されます。前期選抜では学力検査を行わないことが特徴です。合否の判定には調査書(内申点)の割合が非常に高くなっています。調査書は中学3年生の2学期までの成績が反映されるので、一学期、二学期の定期テストの結果が重要です。テスト結果の他に授業態度や課題の提出状況なども内申点に加味されます。
調査書にはその他に部活動や生徒会活動、校外活動などの特別活動の記録や出席状況などが記載されます。推薦入試で受験を検討している生徒さんは日ごろから定期テストで点数を重ねることや課題にしっかり取り組むことなどを意識して学校生活を送りましょう。 また前期選抜は学校からの推薦が不要でだれでも受験が可能なため、倍率は非常に高くなっています。毎年倍率が2倍以上になる学校・学科も多く、前期選抜で人気の学校に合格することはなかなか難しくなっているようです。前期選抜の対策だけではなく、後期選抜も視野に入れて受験の準備を行いましょう。