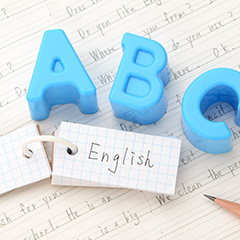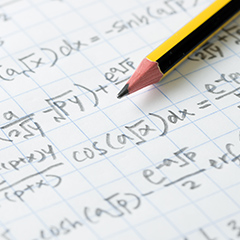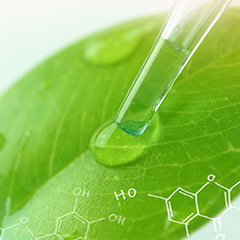あなたの今の偏差値や学習状況がどんな状況でも、私たちは杏林大学医学部合格への道のりを提示できます。
医学部専門プロ教師による
杏林大学医学部専門対策

偏差値が届いていなくても、杏林医学部に合格ができる理由

いきなりですが、模試で出る「偏差値」とは何でしょうか?
簡単に言えば、「総合力」のことです。つまり、あなたの偏差値が64.7あるとすれば、杏林医学部に合格できる「総合力」があることを表しています。
ここで問題なのは、偏差値が64.7であることと杏林医学部の入試問題が解けることはイコールではないということです。
ためしに、自分の偏差値より下の大学の過去問を解いてみてください。合格点を取れるものもあれば、まったく太刀打ちできない大学もあるはずです。
上記の理由から、偏差値が64.7あっても杏林医学部に合格できないこともあれば、偏差値が届いていなくても杏林医学部に合格できるという現状が生まれているわけです。
まとめますと、「入試本番で杏林医学部の入試問題が解けたかどうか」
最終的にはこれで全てが決まることになります。
偏差値に届いていない場合に、私たちがやることが決まりましたよね?
入試本番までに、杏林医学部の入試問題が解けるようにすること。これができれば、今偏差値が届いていなくても、杏林医学部に合格することができます。
杏林大学医学部に受かるためだけに特化した勉強法に切り替えましょう
偏差値はあくまで目安です。
事実私たちは、激戦区東京(首都圏)で25年間、数多くの逆転合格の実績を残してきました。
入試本番では、満点を取る必要はありません。
解くべき問題、解かなくていい問題を確実に見抜き、「杏林大学医学部の専門対策」で学んだ問題だけをスラスラと解いていく。
そして、合格最低ラインを100%超えていく。
これが、私たちが実践している、模試の偏差値にとらわれない、入試本番で合格最低ラインを確実に超えるための志望校対策です。
具体的には、下記で紹介する杏林大学医学部の入試問題の傾向に沿った対策を考えていくことになります。
杏林大学医学部 入試問題の特徴と傾向
-
英語
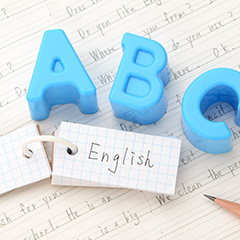
他大学よりも語法に関する出題が多い
杏林医学部の英語では、文法・語法の大問数が多いこともあり、様々な分野からまんべんなく出題されています。他の医大よりも語法に関する問いがあり、形容詞や副詞がやや多めです。さらに、誤文訂正問題が出題されるため、品詞や、各単語の用法などの理解が大切といえるでしょう。
杏林医学部の長文読解は、(英文1)と(英文2)に分かれて出題されており、そのトピックは医学に関連するものが頻出となっています。設問は、空所補充や同意表現、内容真偽のほか、内容説明や主題を問うものもあります。
-
数学
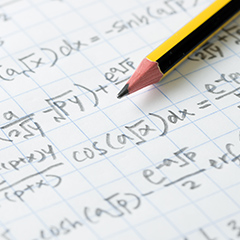
指数関数・複素数平面の対策に穴がないか注意
杏林医学部数学は、過去5年で「微積分法」が例年必ず独立した大問で出題されています。小問集合で問われるのは、「整数の性質や数列」「極限」「確率」などです。「指数関数」は、他に取り扱われる大学が、日本医科と東邦大に絞られる上、2年連続で出題されてます。また、「複素数平面」については、私大医学部で最も出題範囲の広い東邦大を除けば、杏林医学部のみの出題です。他大学ではあまり見ない出題の特徴として、「場合の数」「集合と論理」からの出題も見られるため注意が必要です。
-
化学

他大学とずれた出題傾向に注意
杏林医学部の化学では、他の私大医学部と傾向がややずれているところに特徴があります。理論分野の「物質の合成と化学結合」の範囲では、独立した出題がこれまでにありません。しかし、同じく理論の「物質の状態」のうちの「気体・溶液」からは過去に何度か出題があります。物質の色や匂いの有無、常温時の状態などといった性質を問うものが比較的多く見られますので、基礎的な事項をしっかりおさえましょう。特に頻出と言えるのは、無機分野の「非金属元素」です。無機物質の知識を、理論と絡めて試す問題も散見されます。
有機は、「有機化合物の分類と分析」、「アルコールと関連化合物」、「芳香族化合物」などが、他の分野と比較してやや幅広く扱われています。
-
物理

運動方程式、気体の状態変化が頻出
杏林医学部の物理は、過去5年で「力学」の運動方程式、「熱力学」の気体の状態変化に関する問題が頻出です。「力学」「電磁気」「熱力学」「波動」の分野から大問1題分ずつ出題されるのが2015年度までのパターンでしたが、2016年度はその形式を踏襲しながらも、大問4で「原子」が出題されているので、今後も注意が必要です。
数値計算と文字式の計算が主で、試験時間に対して問題量は多いため計算力で差がつきます。広範囲の出題で、問題は教科書レベルが中心となりますが、数問は難度の高い問題が出題されます。
-
生物
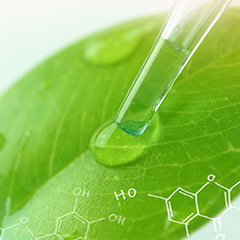
遺伝情報・体内環境が過去5年で8回出題
杏林医学部の生物は、1つの問題に複数の分野が関連していることが多く、偏った知識では太刀打ちできないところに特徴があります。さらに、設問は「正しいものをすべて選べ」といったように、正解が複数設置されているものが多数あり、正確な知識が求められています。
医学部入試の生物では医学に密に関連する分野が好んで出題される傾向にありますが、杏林医学部に関しては幅広い分野から出題されます。その中でも出題頻度の高いと言える分野は「遺伝情報」「体内環境」で、過去5年で8回出題されています。毎年どちらか、あるいは両方の分野から大問1~2題以上は出題されているということです。次いで「生殖・発生」も多く出題が見られます。
いかがだったでしょうか?
これらの専門的な対策を全て1人でこなすのは、困難といわざるを得ません。
その時は、私たち医学部専門のオンラインプロ教師をご検討ください。
あなたの今の偏差値や学習状況がどんな状況でも、私たちは医学部合格への道のりを提示できます。
医学部専門プロ教師ができること
- 激戦区東京で高い実績を残したプロ教師が指導します。医学部の専門家です。
- 合格するためのスケジュール管理・計画が渡され、あなたの弱いところ・苦手な部分をピンポイントで解決してくれ、効率よく成績を伸ばすことができます。
- 杏林大学医学部についての話や自分が本当に合格できるのか不安な点を常に相談でき、モチベーションを維持してくれます。
- 杏林大学医学部の傾向・特徴に沿った専門対策をしてくれることで、確実にあなたを杏林大学医学部合格に近づけてくれます。
プロ教師が語る科目別勉強法 一覧
杏林大学医学部の基本情報
| 学校名 |
杏林大学 医学部
三鷹キャンパス 〒181-8611 東京都三鷹市新川6-20-2
・JR中央線・総武線「三鷹駅」より、『晃華学園東行』バスで「杏林大学病院前」下車/『野ヶ谷』行バスで「杏林大学病院入口」下車
・JR中央線・総武線・京王井の頭線「吉祥寺駅」より、『野ヶ谷行』、『深大寺行』バスで「杏林大学病院入口」下車
|
| 試験種類 |
・一般入試
・センター試験利用入試
・東京都地域枠(奨学金)入試
・茨城県地域枠(奨学金)入試
・外国人留学生入試
・編入学・転入学入試 ※2019年度実施なし
|
| 試験科目(一般入試) |
▽第1次試験
▼英語:コミュニケーション英語I・コミュニケーション英語II・コミュニケーション英語III・英語表現I・英語表現II
▼数学:数学I・数学II・数学III・数学A・数学B (確率分布と統計的な推測を除く)
▼理科:【物理、化学、生物】の中から問題配付後に2分野を選択
▽第2次試験:
▼小論文
▼面接
|
| 配点(一般入試) |
総点:350点
・英語:100点
・数学:100点
・理科:150点(各科目の配点は75点)
|
| 日程(試験、合格発表)(一般入試) |
・一般入試 前期日程
出願期間: 2018年12月10日(月) ~ 2019年1月18日(金)
(WEB出願登録・検定料振込)出願開始日9時~出願締切日17時
(出願書類郵送)出願締切日必着
一次試験日:2019年2月1日(金)
一次試験 合格発表日:2019年2月7日(木)14時~
二次試験日:2019年2月11日(月・祝)
二次試験 合格発表日:2019年2月14日(木)14時~
・一般入試 後期日程
出願期間:2019年2月4日(月) ~ 2019年2月25日(月)
(WEB出願登録・検定料振込)出願開始日9時~出願締切日17時
(出願書類郵送)出願締切日必着
一次試験日:2019年3月4日(月)
一次試験 合格発表日:2019年3月8日(金)14時~
二次試験日:2019年3月10日(日)
二次試験 合格発表日:2019年3月13日(水)16時~
|
| 定員(一般入試) |
・一般入試前期:91名(一般枠79名/東京都地域枠10名/茨城県地域枠2名)
・一般入試後期:10名
|
| 試験結果、合格者(現浪別)(2017年度一般入試結果) |
・2018年度 一般入学試験結果
受験者数:2,742名
合格者数:145名
倍率:18.91倍
・2017年度 一般入学試験結果
受験者数:2,764名
合格者数:123名
倍率:22.47倍
|
| 再受験生向け |
|
| 奨学金 |
▼杏林大学奨学金(給付型奨学金)
対象:人物・学業成績がともに優れ、修学継続の熱意があるにも拘わらず経済的理由により修学が困難な者。
金額:月額30,000円(年額360,000円)
▼日本学生支援機構第一種(無利子)(貸与型)
資格:人物・学業ともに優れた学生であって、経済的理由により修学が困難な者。
金額:月額30,000円、54,000円、64,000円(自宅外通学者のみ) より選択貸与
▼その他
|
| 卒業後、進路 |
臨床研修医
|
| 関連病院(ジッツ) |
杏林大学医学部付属病院
|
| 同じレベルの学校(併願·志望校調整) |
東北医科薬科大学(私立・偏差値64.8)
金沢医科大学(私立・偏差値64.5)
帝京大学(私立・偏差値64.3)
旭川医科大学(国立・偏差値65.0)
|
| 偏差値ランキング中での順位(難易度ランキング中での順位) |
偏差値ランキング67位(64.7)
|
| カリキュラム |
第1学年
高校時代に学習した生物や化学などの基礎科学の知識を発展させ、医学物理、代謝生化学、生体化学、医学統計学など、医学にかかわる科学の基礎知識を学習する。
同時に、医師に求められる基本的姿勢および知識を学ぶ。とくに医療科学では、「医療と文化」、「医療と社会」などの講義や「OSCE患者体験」を通じて、社会が医師に求める姿勢・態度、そして患者から期待される医師像や医療のあり方を学習する。また、「臨床医学入門」や「病院実習」などを通して、先輩医師と交流しながら、医師のキャリプランを考える。
それと共に「地域と大学」では、三鷹市の現状、我が国における医療システム・福祉システム等に関する講義・グループ学習・演習等を行う。
チュートリアル教育は、「与えられた課題からその背後に存在する問題、追求すべき問題点を見出し、必要な情報・資料を検索しつつ、解決に至る道筋を自ら見出す能力を育成する」ことを目的とした教育である。将来、医療の現場で様々な問題に遭遇した際、日々進歩する膨大な医学知識の中から適切な情報を抽出し、これを解決してゆくための方策を学ぶ。
分子生物学と肉眼解剖学の講義により、人体の構造の理解や生命の根源にせまる学習することは、医学の基本的知識習得の第一歩を踏み出すことになる。
英語によるコミュニケーション能力は、医師はもとより、国際化の進んだ現代の社会人には、将来の活躍する世界を広げるために不可欠である。英語・医学英語Iでは、その重要性に鑑み、学生を能力別に小グループに分け、それぞれの実力に合った演習型の講義を行う。
また、原則として金曜日は井の頭キャンパスで講義を行い、専門外の学問や他学部の学生と交流する機会としている。学問的関心により他学部に出向いて授業を受ける「他学部履修」の制度を利用することは、広い分野の学問を体験する好機でもある。大学生として深い教養を身につけるために、積極的に自ら考えて学ぶ姿勢が習慣となるように努めてほしい。
第2学年
基礎医学を学ぶ重要な学年である。解剖学(肉眼解剖学及び組織解剖学)では、すべての医学の基礎となる人体の構造を学ぶ。統合生理学・細胞生理学・細胞生物学・感染症・免疫学などの基礎医学科目を学び、同時に実習が行われる。これらの科目は『人体の構造と機能』を理解する上できわめて重要なものである。将来の医師としての生涯学習の土台となる基礎医学を学ぶ重要な学年であることを自覚し、基礎医学科目の徹底した修得を目指してほしい。
医療化学Bでは、医師としての生涯学習の方法や患者と医師関係の在り方などを考えるために、医療情報、コミュニケーション、カウンセリング、基礎生命科学、キャリア・ワークバランスなどについて学習する。英語・医学英語IIは、学生を能力別の小グループに分け、それぞれの実力に合った演習型の講義を行う。
第3学年
前期は、薬理学、病理学などの基礎医学科目が配置されている。これらの科目は、第2学年までに学んだ人体の構造と機能の上に、さらに「病態」の要素が加わったものであり、その知識や考え方は、医師として患者の病態機序や薬剤の作用機序などを考えるための基礎となる。さらに社会と医学を結ぶ科目として衛生学を学習する。また、臨床系科目の学習が開始される。先ず臨床医学総論、臨床検査医学・輸血学が行われた後、消化器内科学、消化器外科学、循環器病学Aが始まる。
後期には、呼吸器内科学、内分泌・代謝内科学、神経内科学・脳卒中医学、血液内科学、腎臓内科学、呼吸器・甲状腺・乳腺外科学、循環器病学B、産科婦人科学、小児科学、精神神経科学、泌尿器科学、皮膚科・形成外科学の各科目が行われる。循環器病学は内科学Ⅱ(循環器内科学)と心臓血管外科学を中心とし、関連する教室からの講義を組み合わせた統合型となっている。他の科目も必要に応じて教室の壁を越えて適切なテーマと講義担当者を配置している。
その他、英語・医学英語IIIでは、少人数のグループで英文医学論文の講読の演習を行うスモールグループ学習が行われる。
第4学年
第3学年後半から始まった臨床医学の講義が引き続き行われる。
和漢医学概論、法医学、高齢医学、リウマチ膠原病学、小児外科学、救急医学、脳神経外科学・脳卒中医学、整形外科・リハビリテーション医学、眼科学、耳鼻咽喉科学、放射線医学・放射線腫瘍学、麻酔科学、腫瘍学、感染症学、生活習慣病学などが含まれる。これらの臨床医学に関する系統的な知識の修得は、臨床実習に際して不可欠で、実地臨床への第1歩である。
次年度の臨床実習に備え、診断能力と基本的な臨床技能を身につけるための臨床診断学講義および実習が行われる。
その他、臨床医学的な内容を課題としたチュートリアル教育、必修科目としての医学英語が行われる。英語・医学英語IVでは、少人数のグループで英文医学論文の講読演習が行われ、さらに高度な英語能力の修得を目指す。
後期には臨床実習が開始される。臨床実習に先だって、これまでに学んだ基礎、臨床、社会医学の知識と基本的な臨床技能に関して、全国的に行われる共用試験(コンピュータ試験CBTと基本的臨床技能試験OSCE)による評価を受ける。共用試験に合格することは臨床実習の要件である。臨床実習を許可されたものには、白衣式において白衣とStudent Doctorの認定証が授与される。臨床実習(BSL)は、これまでに修得した医学知識を、実地臨床に応用する能力の育成が目的であり、ほぼ2年間にわたって小グループで各科を廻って行われる。臨床医としての姿勢の基本がこの時点に形成される。
第5学年
M4後期に引き続き、臨床実習が主体となる。当学年では、臨床実習として、学生の診療参加型実習(クリニカルクラークシップ)が積極的に取り入れられている。自らが、担当する患者の担当医になったつもりで患者の病歴を聴取し、課題を解決するための検討を積極的に行う。これまでに修得した医学知識を応用する場である。積極的に臨床実習の課題や疑問を解決していく姿勢が望まれる時期である。疑問を感じたら各科の先生に積極的に質問し、知識を確実なものにするなど、生涯医師として学習するための良い習慣を身につけて欲しい。
第1から4学年に引き続き、さらに高度な英語力を身につけたいと希望する学生、第6学年で国外でのクリニカルクラークシップ実習を希望する学生等を対象にした英語・医学英語Ⅴを選択科目として設定している。
第6学年
最終学年は、卒業に向けて全科目の総仕上げと、卒後臨床研修への円滑な導入のための準備に充てられる。
診療参加型臨床実習であるクリニカルクラークシップが、第5学年に引き続き行われる。学内もしくは学外(海外を含む)の医療機関で各2〜4週間の実習に臨む。その後、6年間の医学知識の総まとめとなる「臨床総合演習」が行われる。また、公衆衛生学の講義において、既習の医学知識の社会集団への応用と医学知識の整理が行われる。
|